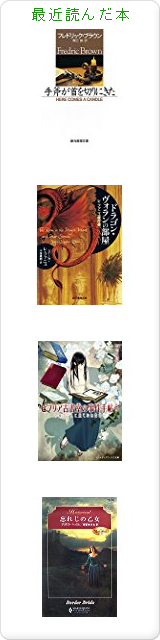真夜中のティータイム
気になった事を気ままに書いていくブログです。 映画、アニメ、小説(SF、ミステリー、ファンタジー)、 ゲーム(主にRPG、格ゲー)の話題が中心になると思われます。
KalafinaのCD「Magia」を買ってきた。かなり売れているみたいだから、ちょっと心配したが、無事に初回限定版をゲットできた。帰宅後、何か買い忘れているな…っと思ったら、麻生夏子の「More more lovers」だった。仕方ない、こちらは来週にでも。
今日のアニメ
・お兄ちゃんのことなんかぜんぜん好きじゃないんだからねっ!! #6「兄は黒パンストの夢を見る!」…勘弁してくれーー。BLはマジ苦手なんだからぁ。
・とある魔術の禁書目録Ⅱ #19「木原数多」
・ケロロ軍曹 #352「ナベベ 闇鍋奉行! であります」
今日のドキュメンタリー
・デンマーク
今日の映画
・男たちの挽歌 A BETTER TOMORROW(韓国/2010年)
ジョン・ウーの「男たちの挽歌(1986年)」のリメーク。若干、最初の人間関係などの状況説明が分かりづらかったり、結末が良くなかったりと不満はあるものの、これはこれでなかなか出来の良い作品になっている。もっとも傑出したオリジナルと比べれば、かなり落ちるが。それでも、兄弟のドラマがラストでかなりの盛り上がりを見せるし、全編を覆う切なさもオリジナルより上。つまりリメーク作としては、上の部類と言って良いだろう。最近、こう言う熱い男のドラマがなかったので、特にそう思えるのかもしれない。あと、クライマックスのド派手な銃撃戦は、一見の価値がある。
今日のアニメ
・GOSICK #6「灰色の狼は同胞を呼びよせる」…涙目のヴィクトリカ、可愛すぎ☆
今日の映画
・踊るブロードウェイ(アメリカ/1935年)
記者のキーラー(ジャック・ベニー)と演出家のゴードン(ロバート・テイラー)の一悶着と、その演出家と同郷の女友達アイリーン(エリナー・パウエル)の恋愛を描いたミュージカル。…なのだが、ストーリーは他愛もない…って言うより、つまらない。はっきり言って、退屈だった。また肝心のミュージカルシーンも、「これがMGMミュージカルか?」ってくらい振付が大雑把。特に印象に残るナンバーもないし、些かガッカリした出来だった。…っとは言うものの、豪華絢爛なレビューシーンや、エリナー・パウエルの上手過ぎるタップダンスなど、見所が多いのも確か。
・「Alice: Madness Returns」の最新ムービー
「不思議の国のアリス」をベースとしたゲームであるが、ムービーを観る限り、狂気とダークさがかなり良さそう。是非プレイしたいが、日本での発売はちょっと無理かな?。
今日のアニメ
・スーパーロボット大戦OG -ジ・インスペクター- #17「鋼の咆哮」
・ひだまりスケッチ #12「12月24日 ChristmasEve」+「12月25日 サヨナラ…うめ先生」(再々見)
今日の映画
・オーシャンズ(フランス/2009年)
海にすむ生き物の生態を収めた海洋ドキュメンタリー。一体どうやって撮影したんだ…って言う部分も結構あり、なかなか見ごたえのある作品になっている。TVのドキュメンタリーではあまり扱わない弱肉強食もちゃんと描いており、悪くない。ただ、「ディープブルー」と重なる部分がかなり多く、その辺りは残念だ。また後半、この手のドキュメンタリーのお決まりである自然保護のメッセージはさすがにどうしたものか。自然保護が悪いと言うのではないが、あまりにも取って付けたようなメッセージで興ざめだった。この映画ならではの切り口を見せて欲しかったよ。
唯のストラップ、ゲット!。これで後残るのは、律だけだ。
今日のドラマ
・カルテット 第3話
今日のドキュメンタリー
・ホープダイヤ
今日の映画
・TEKKEN 鉄拳(アメリカ/2009年)
ナムコの同名格闘ゲームの映画化。…なのだが、これは酷い。スタッフはゲームを理解して、映画化しているのだろうか。キャラはとりあえず似せているが(マーシャル・ローはまったく違うけど)、ストーリーは全く別もの。まぁ映画とゲームは別ものなので別に同じストーリーにする必要はないのだが、それにしてもゲームを元にしているとは思えない内容だ。悪く考えれば、「鉄拳」の知名度を借りたにすぎない。しかしそれ以上に酷いのが、アクションシーン。色々な格闘技が出てくるのに、動きが似たりよったりで、どれもマーシャル・アーツにしか見えない。特にカポエラとサンボは、どこがじゃ…って感じだ。結局、アメリカ人の格闘技に対する認識はこの程度のものなんだな。もっともそれ以前に、ストーリーがつまらない、アクションが迫力ない(役者のアクションがヘタクソ過ぎ)、展開がダラダラしている…っと、とても見れたものじゃないけど。やはりゲームの映画化には、ロクなものがない。
未だになっちゃんの「More more lovers」が頭から離れない(笑)。
今日のアニメ
・かみちゅ! #6「小さな決心」(再見)
・スター・ウォーズ/クローン・ウォーズ2 #19「コルサント炎上」
・君に届け 2ND SEASON #4「わかってない」…今期はすれ違いと、すっ呆けたギャグが中心だな。
今日の映画
・録音霊(キングレコード/2001年)
一応、心霊ホラーなんだが、まったく怖くない。はっきり言って、監督、脚本共に才能なし。大体、出てくる連中がとても音楽関係者に見えない。あれじゃ、単なるチンピラかゴロツキだ。見れる部分がまるでない、最低の作品だった。観るだけ、時間の無駄。
昨日と今日のアクセス数、半端じゃねぇ(このブログにしては)。やはり、「アニうた」の影響かな?
私がビデオテープで持っている作品の中には、DVDで発売されてないものが結構ある。出来れば、セルDVDで保存したいところなんだが、一向に発売されない。そんな訳で、それらの作品をデジタルに変換しようと思い立った。まずは今日、1本目をデジタル化した。その1本目は、これだぁぁ。「水滸伝」!(丹波哲郎が廬俊儀をやったあれとは違うぞ)
今日の映画スペシャル
・水滸伝(中国/1983年)
原作「水滸伝」の第74話の泰山での武術大会のエピソードを中心に映画化した作品。個人的には「水滸伝」の映画化の中でも最高傑作と思っているし、カンフー映画としても上位にランクされる映画だと思っている。…なのに、Blu-rayどころか、DVDでさえ発売されてない不遇な作品。私も昔、ビデオテープに録画したものを一つだけ持っているにすぎない。何だかなぁ。さて、本作の見せ場はほぼ全編で繰り広げられる格闘アクション。とにかく本物の武芸者が大挙出演しているので、その迫力が違う。動きが綺麗なうえに、半端じゃなく早い。中でもクライマックスの御前試合のシーンは、凄まじすぎる。もう、これを観ると、どこぞのカンフーもどきの映画なんか観れなくなるよ。それ以外でも、合戦シーンなんかもあって、実に楽しい作品になっている。
せっかくだから、今回は少し詳しく紹介する。まず、登場人物から。
最初は宋江(↓)。今回は彼の為、梁山泊の面々がピンチになる。原作通りのヘタレっぷりが、如何にも宋江って感じでイイ。
次(↓)、左が呉用で、右が廬俊儀。呉用は名前を言われなかったが、軍師と言われていたので間違いないだろう。
左(↓)から、李逵、一人飛ばして、扈三娘、林沖。林沖も名前を呼ばれなかったが、まず間違いない筈。
阮三兄弟(↓)。あれ?、一人足りないや。これ以外でも多くのキャラが登場するが、説明がまったくないので、誰が誰やら。あと、クライマックスに登場する主要キャラは後ほど。
本作は最大の見せ場は、何と言ってもクライマックスの御前試合。5vs5の試合を行うことになるのだが、なんと宋江が人質にとられ、試合に勝てば、宋江を殺すと脅される。梁山泊の面々は英雄豪傑ぞろいなので間違いなく勝てるのだが、この脅迫によって、実力を出せなくなる。そんな中での第1試合。まずは花和尚・魯智深(↓)。途中、止めを刺しそうになるが、脅迫を思い出し、あえなく敗北。
第2試合。九紋龍・史進(↓)が登場。彼も圧倒的な強さを見せるが、脅迫の為、敗北。
第3試合。今度は武松(↓)。もう後がない梁山泊。これで負けたら、梁山泊組の負け。でも脅迫の為、力が出せない武松。どうする、梁山泊。
…っと、そのとき、燕青が宋江を救出して戻ってきた。これを確認すると、武松、一気に酔拳のスタイルへ(↓)。もう、この辺りは本編中、最高に痛快なシーンだ。圧倒的な強さで、相手をボコボコにして勝利。
第4試合。石秀(↓)が登場。相手が素手だと思い、こちらも素手で挑む。だが、実は相手は武器を隠し持っていた。でも、そんなの目じゃない。相手を完膚なきまでに打ちのめして、圧勝。
そして、第5試合。宋江を救出した燕青(↓)が登場。燕青が秘宗拳(燕青拳)の使い手で、梁山泊でも上位にランクされる強さを持っている。だが、今度は相手も強敵。苦戦の末、何とか勝利。
策略に失敗し、頭にきた高(イ求)。一味を捕まえろと、兵で彼らを取り囲む。だが、すでに周りには梁山泊の残りの面々が。逆に高(イ求)をとり囲んで、END。いや~、久しぶりに観たけど面白かったぁ。やはり、DVDで良いから出してくれよ>メーカー
今日のアニメ
・IS<インフィニット・ストラトス> #3「転校生はセカンド幼なじみ」…先週とは打って変わって、セシリアがむちゃくちゃ可愛くなった。ツンの時期がほとんどないツンデレだな(笑)。
・夢喰いメリー #3「夢の向こうから」
・海月姫 #10「愛とぬるま湯の日々」…いや、体に合わせて切ったって、ドレスにはならないって(笑)。
・屍鬼 #21「第腐汰悼と悲屠話」
・魔法少女まどか★マギカ #6「こんなの絶対おかしいよ」…魔法少女は実はゾンビ…って、どんどん救いのない話になるなぁ。
今日のドキュメンタリー
・アイスランド